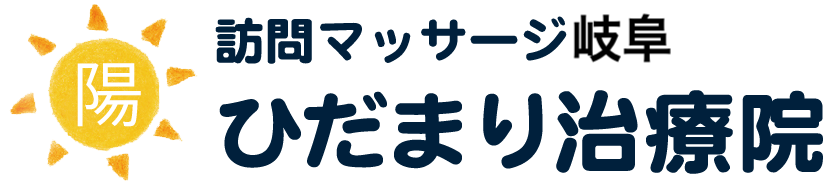訪問マッサージと訪問リハビリの違い(2025年版改訂パート2)
訪問マッサージと訪問リハビリは、在宅で受けられる専門的なサービスですが、その目的、提供者、保険適用などに明確な違いがあります。適切なサービスを選択するためには、それぞれの特徴を理解することが重要です。
前回の「こちらの記事」でもお書きしましたが、更に加筆してご説明しようと思います。」
1. 目的と専門性
- 訪問マッサージ:
- 目的: 主に、疼痛緩和、血行促進、筋緊張の緩和、関節可動域の維持・改善などを目的としています。あん摩マッサージ指圧師が、なでる、押す、揉む、叩くといった手技を用いて施術を行います。
- 対象となる症状(医療保険適用時): 麻痺、関節拘縮、筋固縮、運動機能障害など、医師が医療上の必要性を認めた場合に健康保険が適用されます。
- 専門性: 東洋医学的な観点も取り入れ、身体のバランスを整えることを重視する場合があります。
- 訪問リハビリ:
- 目的: 主に、要支援・要介護者の身体機能や生活機能の維持・向上、日常生活動作(ADL)の改善、寝たきり予防、社会参加の促進などを目的としています。
- 提供者: 理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などが、それぞれの専門知識に基づいて評価・計画を作成し、運動療法、作業療法、言語療法などのリハビリテーションを提供します。
- 保険適用: 医療保険に加えて、介護保険も適用されます。介護保険を利用する場合は、ケアプランに組み込まれる必要があります。
- 専門性: 医学的な知識に基づき、個々の状態や目標に合わせた具体的な訓練や指導を行います。
2. 保険適用
| 項目 | 訪問マッサージ | 訪問リハビリ |
|---|---|---|
| 主な保険 | 健康保険(医師の同意が必要) | 医療保険、介護保険(要支援・要介護認定が必要、ケアプランに組み込み) |
| 対象となる状態 | 麻痺、関節拘縮、筋固縮、運動機能障害など、医師が医療上の必要性を認めた場合 | 要支援・要介護状態にある方で、身体機能や生活機能の維持・向上、日常生活動作の改善などを目的とする場合 |
| その他 | 医療保険の自己負担割合による | 医療保険・介護保険それぞれの自己負担割合による。介護保険には支給限度額あり。 |
Google スプレッドシートにエクスポート
3. 併用について
以前の記事と同様に、訪問マッサージと訪問リハビリは併用が可能です。例えば、脳卒中後の麻痺がある方が、訪問リハビリで歩行訓練や日常生活動作の練習を行いながら、痛みや筋肉の緊張を緩和するために訪問マッサージを利用するといったケースがあります。
4. 利用の流れと注意点
- 訪問マッサージ:
- かかりつけ医に症状を伝え、訪問マッサージが必要であるという同意書を作成してもらいます。
- 訪問マッサージを提供する事業所を選び、契約を結びます。
- 同意書と保険証を事業所に提出し、施術開始となります。
- 訪問リハビリ:
- かかりつけ医やケアマネジャーに相談し、訪問リハビリの必要性を検討します。
- 介護保険を利用する場合は、ケアプランに訪問リハビリを組み込んでもらいます。医療保険のみを利用する場合は、医師の指示書が必要となる場合があります。
- 訪問リハビリを提供する事業所を選び、契約を結びます。
- 医師の指示書やケアプランに基づき、リハビリテーションが開始されます。
5. どちらを利用すべきか
どちらのサービスが適切かは、個々の身体の状態やニーズ、そして医師の判断によって異なります。
- 痛みの緩和や筋肉の緊張の緩和、リラクゼーションを主な目的とする場合は、訪問マッサージが適している可能性があります。
- 身体機能の維持・向上、日常生活動作の改善を主な目的とする場合は、訪問リハビリが適しています。
訪問マッサージ 訪問リハビリ 違い判断に迷う
訪問マッサージ 訪問リハビリ 違い判断に迷う場合は、まずはかかりつけ医やケアマネジャーに相談し、それぞれの専門家からの意見を聞くことが重要です。医師は、症状や状態に応じて適切なサービスを判断し、必要な書類(同意書や指示書)を作成してくれます。
2025年に向けて
高齢化が進む日本において、在宅での医療・介護サービスの重要性はますます高まっています。訪問マッサージと訪問リハビリは、それぞれ異なる役割を担いながら、地域包括ケアシステムの一翼を担っています。利用者は、自身の状態や目標に合わせて、これらのサービスを賢く選択し、より質の高い在宅生活を送ることが期待されます。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご質問ください。